- 2026年卒
- 2027年以降卒
INTERVIEW
2017年入社
環境科学研究科修了
CAREER STEP
| 1年目 | 西日本製鉄所 製鋼部 第2製鋼工場 転炉担当。工場の安定操業やコスト削減のための実験を実施。 |
|---|---|
| 2年目 | 西日本製鉄所 製鋼部 製鋼技術室 精錬担当。転炉・二次精錬のコスト削減のための実験を実施。 |
| 3年目 | 同上。建設担当へ 転炉・二次精錬の新規設備設置検討のための研究開発業務に従事。 |
| 4年目 | 同上。厚板品質担当へ 厚板材の品質改善や連続鋳造用機能材の新規開発を担当。 |
| 5年目 | 同上。建設担当へ 連鋳、鋼片職場への新規設備導入/能力向上への投資に携わる。 |
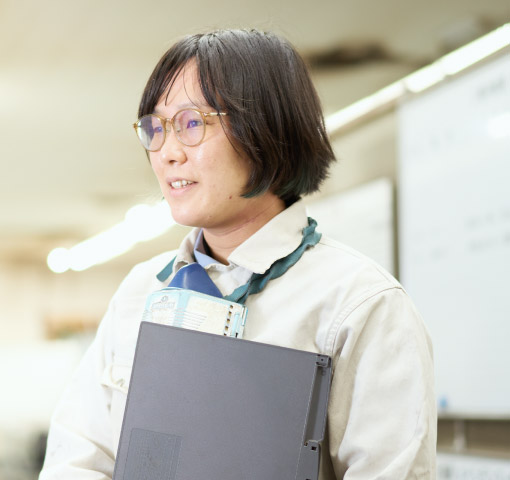
大学院では溶融非鉄金属の熱物性値について研究していました。将来は産業の基盤となる素材業界に関わりたいと思い、鉄、非鉄、セラミックスなど素材系の企業を中心に、インターンシップや会社説明会に参加。その中で鉄鋼業に関心を抱いたのは、ある製鉄会社のインターンシップに参加したことがきっかけです。数百トンもの鉄鉱石が高炉で溶かされ、精錬されていく工程のダイナミックさに圧倒されました。
最終的にJFEスチールを選んだのは、対応してくださったリクルーター・面接官の人柄や、醸し出す柔らかな雰囲気に惹かれたから。基本的な仕事内容が同じならば、自分にマッチした文化や風土を持つ企業がいいと思って、いちばん自分が気持ちよく働ける職場だと判断して入社を決意しました。
配属された製鋼部は、製銑工程で溶かした鉄から転炉で不純物を取り除き、加工しやすい“鋼”に造り変える製鋼工程を受け持つ部署です。溶けた鋼は連続鋳造機で固められてスラブとなり、熱延、冷延、条鋼工程へと送られます。

製鋼部内で私たち総合職は、工場の安定操業やコスト削減を目的に、担当する工程改善のための各種実験を行うほか、新規設備設置検討のための研究開発、投資検討などを行っています。例えば私が2年目に担当したのは、転炉・二次精錬の工程改善です。銑鉄は炭素をはじめとする不純物を含んでおり、それらを転炉・二次精錬で除去します。不純物のひとつであるリンは石灰に取り込ませて除去しますが、石灰を溶解させるために酸素を吹き込む必要があります。もっとも効率よく、より少量の石灰で不純物を取り除くためにはどうすればよいのか。その酸素量や吹き込むタイミングなどを最適化させる条件を各種実験から導くことが、私の役割となります。製鉄は長い歴史を持ちますが、扱う原料により変化する溶銑の質やお客様からの要求品質によって、細かく、また柔軟に精錬条件を調整しなくてはなりません。不断の改善が必要なのです。
また、建設担当は新規設備設置検討のための研究開発や能力向上への投資検討を行います。近年では転炉や二次精錬の工程をサーモカメラで監視し、画像解析技術を用いることで、操業における現場作業者のアクションタイミングの補助を図るシステムの導入検討などを行いました。こうしたいくつかのプロジェクトを同時並行で進めています。


入社4年目に連続鋳造の品質管理を担当していた時、スラブの品質が不安定になったことがありました。ただちに原因究明に努めましたが、さまざまな条件が複合しているため、原因特定にはかなりの困難が予想されました。私はそれまでに蓄積された不具合のデータから条件ごとの発生率を解析し、蓋然性の高い原因にあたりをつけて実験・検証を行い、不具合の原因を特定することができました。このように自分自身の手で目に見える効果を出せたときは胸がすくような達成感が得られます。
また、新規設備の投資では、設備の規模が大きく稼働環境も厳しいため、必然的に工事規模が大きくなり、他部署との調整や検討がうまくいかないことも多々あります。そんな場合でも現場、他部署、先輩後輩やデータの解析からいろいろな知見を得て、どうにか形になったときにやりがいを感じます。一方、設備投資は金額が大きく、自分の判断や裁量でスペック等が簡単に変わってしまうので、プレッシャーを感じることもあります。そのため、同様の業務を担当していた先輩方や現場のキーマンにヒアリングを行い、自分なりの最善を追求するよう心がけています。
あとは体調管理が重要ですね。製造所は24時間稼働しているため、自分が担当する設備で夜間に問題が発生した場合や、実験のタイミングが夜中になることも少なくありません。できるだけベストなコンディションを保つようにしています。
2017年にデータサイエンスプロジェクト部が設立されたように、近年、当社ではデータ活用による操業の効率化を図るため、データサイエンスを取り入れる機運が高まっています。私も設備投資の際に、データサイエンスを絡めて効率化や高精度化を図りたいと考えており、SPSSなど解析・モデリングツールの学習を始めました。各種ツールの使い方についてはデータサイエンスプロジェクト部のメンバーが講師を務める研修会が開催されるほか、コンサルティング会社から説明を受ける機会もあり、データサイエンスを学ぶ環境には恵まれていると感じます。
具体的なキャリアビジョンを描いているわけではありませんが、データサイエンスを含めて自身のスキルを高め、ナレッジを深めていくことが重要だと考えています。
コロナ前は、同期や大学時代の友人と一緒によく海外旅行に出かけました。現在は感染対策を万全にして国内旅行を楽しんでいます。私は大学まで東北で生まれ育ったため、中国・四国など西日本を中心に巡り、東北とは異なる自然を楽しんでいます。
